植物はエイリアン?インターネット?
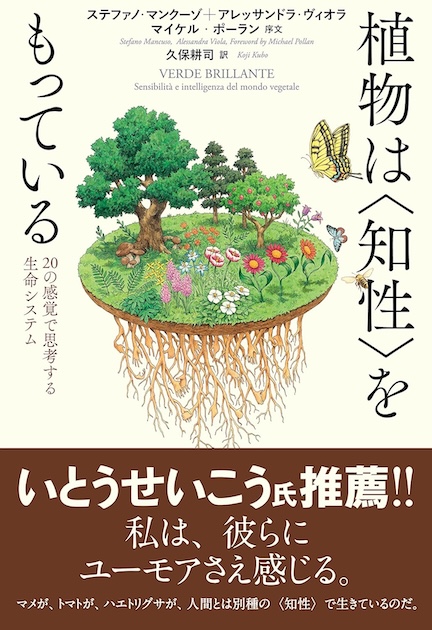
人が花を見て美しいと感じることも
実は植物が人間を操って、世界に広がっていく手伝いをさせるための植物の戦略ではないか
人間界のヒエラルキー(身分制度・ピラミッド型の階層組織)では低下層である植物。
しかし「地球」という一つの惑星の99%を支配している、最も優れた生物 それもまた「植物」。
植物が無いと動物や人間は生きていけないということは、誰もが認める事実だとは思います。
では植物が私たちと同じように「感じ」「眠り」「動き」「狩りを行い」「肉を食べ」「戦い」「商売」をするとしたら?
事実、植物は人間のように周辺の変化を「感じる」感覚があり、しかもその感覚が人間でも せいぜい第6感までなのに対し、植物は、少なくとも20種類は存在しているということが確認できています。
植物が植物の観点で 物を見て、においを嗅ぎ、味を区別し、触られたことを認識し、音を聞くことが出来る。
さらには
・動物が持たないたくさんの感覚を使い、植物の仲間同士でコミュニケーションをとること
・危険を察知する能力によって考えだされた方法で、集約された防衛軍(昆虫など)で身を守ること
など人間には出来ない能力も備えているのです。
※他にも、歳をとると植物も人と同じようにあまり眠らなくなっていくという事実もあるとのこと。 P154/P208
このような植物の持つ未知の能力の答えを、我々人間が、興味深く研究することが、今後 生物界にとっての重要な メカニズムの解明に繋がり、しいては人間にとって益々有益な情報を得られるチャンスでしかないと著書では繰り返し熱く書かれています。
人間ヒエラルキーにおいて、古くから 植物はただの「モノ」という存在でした。
動かない=魂が無いモノという理由で、もはや「生物」ということ自体も微妙な存在でありました。
そのような考え方が一般的な風潮の中、「植物は眠る」という説を唱えた学者リンネ
※但しリンネであっても当時は「植物が食べるという行為」は認めていない
植物が人間のように眠るということ自体、割とセンセーショナルな内容だったとは思います。
しかし当時、それを聞いた学者たちはこの研究結果にはあまり関心を示さなかったようです。
なぜなら、リンネが生きていた当時、まだ「睡眠」という行為が人間や動物に特別な機能があると知られていない時代でした。そのため植物が眠るか眠らないかという問題など、特に重要視されることではなかったからです。P31
それから約100年後に現れた著名なダーウィン。
彼は晩年、世間に「植物は動く」ことや「植物の根には人間の脳に似た機能がある」ことを発見するのです。
しかし この偉大な学者ダーウィンの研究結果であっても、当時の学者達の反応は冷ややかなものした。
「著名人も気まぐれで変なことやっただけ」「単なる気晴らし」などと無関心だったのです。
(そして、このような反応になることはダーウィン自身も想定の範囲内)
ダーウィンは亡くなるまでの間も、慎重に研究内容を発展させていました。
そして彼の死後、その意志を引き継いだダーウィンの息子フランシス。
彼は、長い間 父と一緒に研究を続けた実績で
やはり「植物は知性を持っている」と確信しました。
のちに満を期した彼は、ある学会でその結果を発表することになります。
結果、この主張は大変な反響を呼び、やがて大きな論争を巻き起こすことになるのです。
植物は
動き(時間の経過がゆっくり過ぎるので人間には止まって見えるだけ)
食べ(例:食虫植物)
繁殖能力もあると唱えた。
それに対しいつも時代も 多くの学者達は
「植物が性なんて不謹慎だ!」「植物が食べるわけなかろう。虫がたまたま落ちただけ」などと、いちいち揚げ足取りに躍起になりがちであるのです。
このような固定概念のもとに成り立っている生物学会のなかで、何らかの評価を得るということは非常に厄介でした。
そのため多くの植物学者は、賞レースに勝つための小技として、同じ研究内容でも
植物だけでなく、プラス 他生物(昆虫や動物など)を絡めるという小技を駆使しました。
これにより、今まで誰にも見向きされない研究結果が、動物というスパイスによって「再発見」される現象を起こしたのです。P42
再発見によってもたらされた研究結果を再認識し、偉大なる研究結果と功績を称えられた学者たちはやがて、ノーベル賞などを受賞することになります。
植物オンリーでの研究は、興味を持たれず、重要視されず、無視されがちなため、賞をもらうために植物を後回し・・。
大事なことが無視される状況だと著者は嘆いています。
もしもリンネやダーウィンの自由で素晴らしく研究成果を、学者達の ※批判を受けることなく肯定的に受け止められる風潮であれば、きっと近年 我々にとって目覚ましい研究功績恩恵の数々が賜れてのではないのだろうかと思われてなりません。
なかなか植物単独での研究を評価されることのハードルは高いようです。
※ダーウィン達が「研究結果が間違いではない」という証明をするための膨大な時間と労力とストレスの心労を、より研究の精度を上げる方向にベクトルを向けることが出来ていたとしたら、今現在の我々の医療や生活の分野もさらに飛躍していたのではないかと思うと、人類にとって非常に残念なことです。現代のところの芸能人や著名人へのSNSの過激な批判行為もこれと似たようなものですが。
人間にとって、まだまだ未知な情報が溢れたエイリアンのような存在である彼ら植物を
「とるに足らない物体」で終わらせず「人間や動物とは違った新たな生命体」として研究するメリットは如何許りか。
植物は必要不可欠な要素というだけでなく、人間へのすばらしい贈り物でもある。私たちはその贈り物を捨ててしまっている。P203
それなのに植物はあらゆる点で知的な生物と認めないのだろう?事実を否定するのではなく,私たちにとって貴重な情報源だときちんと認めて参考にする方が得策ではないだろうか。P170
かつて アリストテレスは
「魂」があるか否かは運動するか否かであるという基準での比較を結びつけたため、動かない植物は「無生物」というレッテルを貼られ、人間界で低いヒエラルキー(生物界での階級)を与えられた。
※実際は動いているのだけれどとてもゆっくりなため人間の目には止まって見える。
植物は「動かない」「感覚を持たない」は全くの誤解である。P200
植物は「太陽と動物の世界を繋ぐ媒体」p201
植物は人間の知性への素晴らしい贈り物・アイデアの宝庫・革新的な解決策 p203
知性とは何か?
生物として「植物は動物よりも下位」という意見に真っ向から挑み、知性がある証拠を示し序列を徹底的に覆していきます。P207
脳が無い、動かない から無生物のように考えてしまうことを植物への偏見と捉え、不当な評価を撤回せよと迫ります。P208
知性とは「生きているあいだに生じる様々な問題を解決する能力」P10
Q 「知性がある」の区別をどう判断するのか?
A 「脳が付いている」「動くかどうか」という人から見た視点ではなく生物としての知性と考えたとき、結局は
「生きているあいだに生じる様々な問題を解決する能力」こそが知性と言えるのではないだろうか?と著者は解いています。
「地上に生息している生物はどれも最先端。中途半端に進化した生物など存在しない」 P34
ココがすごいぞ植物
花が昆虫や鳥などを使って受粉を手伝わせる様子を想像してください。
花は動けません。
空高く飛び回る鳥を、地面近くにいる自分のところまで引き寄せなければならないのです。
もちろん、人間のように声を出すことも、手を叩くことも振ることも出来ませんね。
距離も離れているので匂いを出しても遠くの鳥には届きません。では鳥側の視点で考えてみましょう。
上空から地上を見下ろす風景。さて、何か食べ物はないかな?
お!あそこに赤い色が見える。あれはきっと何か食べ物だ!
そう、この時 鳥は視覚で花を察知することが出来ました。
では次に、上空に飛んでいる側からは 色の識別がつかないとしたらどうでしょう?
例えばコウモリ。コウモリはほとんど目が見えません。
う〜ん、色がわからないんじゃ花は見つけられないですよね・・。
しかしそれを見つけることが出来る方法があるのです。
しかもかなり正確に、数ある中から特定の植物のみをすぐに探し出し辿り着く方法が。
それがアメリカの砂漠地に生えているサボテンなのですが、この植物は自分の持つ
衛星放送用のパラボラアンテナそっくりの形をした丸い葉を使うことで、コウモリの
発する超音波を反射して、花の存在をコウモリに知らせるのです。P147
※目があまり見えないコウモリは喉から超音波を発し、その反射音(エコー)を聞き取り反響定位によって、対象物までの距離や方向、大きさ、構造などを把握します。
このような例は著書のほんの一部にすぎませんが、他にも様々な仮説や事例は見ていて飽きません。
・人や動物と植物の身体の仕組みの違い
人や動物→脳や臓器など大事なところをやられたら死ぬ。致命傷を負う。一箇所のみである。集中している。
植物→モジュール形式。どこを切られても生きていける。再生可能。致命傷を負わない。中心に心臓が無い。
この本は そんな様々な可能性と未知の世界を秘めた植物に対し、無関心なうえ、身勝手で意味不明なマウントを取り続けた人間優位の階層時代に戦いを挑む一人の学者の熱い思いがこもった一冊です。
この書籍、私個人は たまたま手にした たくさんの中の一冊にすぎませんでした。
が、読み始めた途端に この著者の日本語に訳されても薄まらない、変態とも言えそうな植物愛の熱量と
植物で賞や評価をもらうことへの様々な困難や苦労も垣間見れ、なかなか知ることのない世界の空気感を感じることが出来、あまりの面白さに驚きすっかりハマってしまいました。
この魅力をぜひたくさんの方に知っていただきたいと心から思っておりますので、よろしければご覧ください。
ご注文はこちらからどうぞ↓
https://amzn.to/4gG5EC8https://amzn.to/4gG5EC8
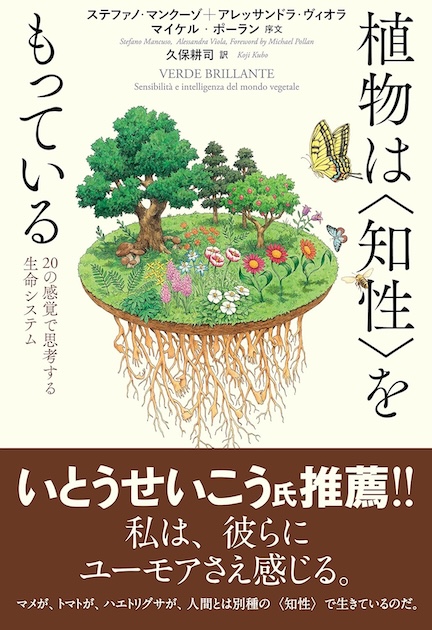
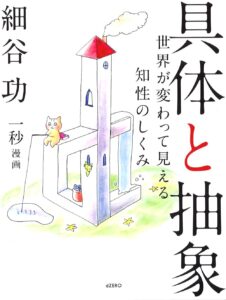
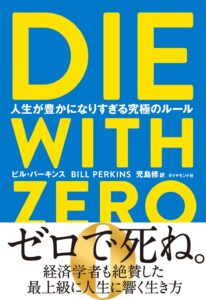
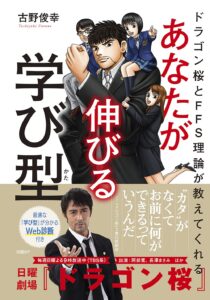
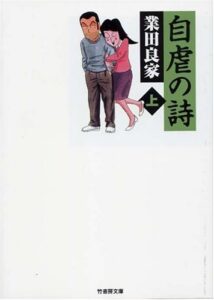

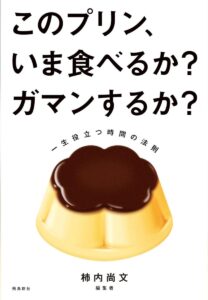
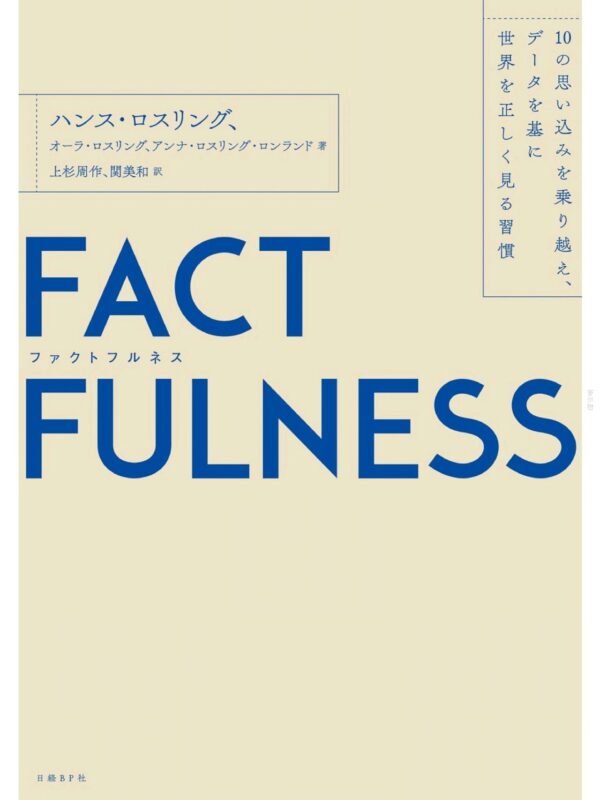
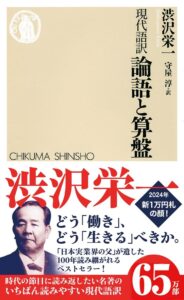
コメント