
今回のテーマは、ウリ・ニーズィー著『その問題、経済学で解決できます』(2014年初版)。
経済学といっても難しくありません。むしろ、「あれ?これ私のことやん…」と何度もなる一冊です。
ある日、いつものように
突然の思いつきで
「新しい趣味を作ろう!カメラを始める!」と カメラ屋さんに向かったカーリーちゃん。
行きは張り切っていた様子だったのに 帰ってから、ずっと機嫌の悪い様子。
どうしたの?と弟のピンカーンが尋ねると・・・

カメラのこと、まだ全然詳しくないって言ったらさ
じゃあこれが一番オススメですよ!って色々出してくれて
思わず買っちゃったんだけど。あとで他のお店も回ってみたら
2倍以上の値段で売られてたのが分かって。
頭きたから返品してやったわ! ああムカつく〜!



ああね。
それはまさしく、この前読んだ本でいうところの
「経済的差別」で出てたパターンだな。
じゃあ僕が、そんなふうにお店にボラれない
魔法の言葉を教えてあげるよ。



はあ?
また小難しいこと言っちゃって。
でも何々?
その魔法の言葉って。
超気になる〜🎵
さすがピンカーン。あっという間にカーリーお姉ちゃんの機嫌を戻してしまいました。
悪意のある差別 悪意のない差別
【経済的差別」ってどういうこと?】
世の中にはさまざまな差別があります。
男女間や性的マイノリティ、人種や宗教の差別、
最近では カーリーちゃんたちの会話にも出てきた「経済的差別」という 差別する側に悪意はないが
お金や収入、社会階層など“経済状況”を理由に 人を不公平に扱う差別。
経済的差別は見えにくく、制度の中に溶け込んでいるため 差別を受ける側が「やる気がない」「サボっている」とすり替えられやすい。(貧しいというだけでチャンスを失い、誤解や偏見まで受ける仕組み)
ではこれらの差別に対し、そもそもこのような問題は何が動機で起こっているのか?(インセンティブ)
その問題を、各自のモラルに訴えるだけでなく 根本的な仕組みをどうすれば解決できるのか?
といったことを 机上の正論ではなく、実際に困っている現場に出向き、
スポンサーから集めた「お金」を使って仕組みから見直し、様々な実験と調査をした地道な行い
その結果をもとに出た結論を、さまざまな事例を挙げて解いているのが今回の著書です。
筆者の二人も学歴などの差別を乗り越え、叩き上げで実績を挙げているので非常にリアリティがある内容です。
彼らは、いずれ同じような差別に遭うであろう可愛い自分の子供たちが 将来少しでも報われる世の中になれば
という願いを胸に今日も熱く「実地実験」を行います。
【報酬が善意を壊すとき】
ここでは「報酬」を出すことで、かえって人のやる気を無くしてしまう、あるいはズルを助長することに気づけます。
報酬やルールには、目に見えないメッセージが含まれているため
善意の行動を無償で行う人に報酬を与える→「あなたのことを信じてない」と伝えてしまうことも。
・報酬は「やる気」を出すが、善意や道徳を壊す可能性もある
例:血液の無償提供に報酬を与えると提供者が減った→「お金のためにやってる」と見られたくない心理が働く
不適切なインセンティブが生む行動の歪み
例:病院に補助金→必要のない治療が急増
例:教師の成果給→テスト対策ばかりになり教育の質が低下→インセンティブが「短期的成果」だけに向くと、本来の目的が壊れる→「測れるものが全てではない」
・報酬をつけると「やらされ感」が生まれ、自発的な善意を潰すこともある
・教育や医療の現場などでは要注意!
・「やる気を引き出す仕組み」のデザインが重要
・人は「意味のある行動」にこそ反応する
・モチベーションは 内発的(善意・使命)×外発的(報酬) のバランスが重要
・寄付・育児・労働・・全て仕組みの設計次第で行動が変わる
【女が男ほど稼げないのは何故か?】
・男女の賃金格差の一因として、競争的な環境を好むかどうかの違いがあり、女性は相対評価による報酬制度の職を避けがちという実験結果も紹介。
※相対評価…集団内の他者と比較して、その人がどの位置にいるかを評価する方式(皆んなの中で私はどのへん?)
多くの環境で、男性は「競争する」ことを求められ 女性は「競争する」ことを求められない中で育った。ただし・・
逆の環境(女性でも小さな時から「自信を持て」「前に出ろ」と励まされるような環境)であれば、女性も競争を好む傾向が見られた。
有能な女性の人材が積極的に現場で活躍できれば、企業や経済もさらに飛躍する機会が増える。
が、雇用する側の人々は「能力のある候補者」の代わりに、より「競争に強い候補者(競争が好きな男性)」を雇う傾向にある。
「ズルい人を嫌いすぎない」ための処方箋
・多くのズルや無責任行動も、仕組みがそうさせている可能性がある
→感情ではなく「制度と構造」のレベルで考えられるようになる。



モラルに頼らず、仕組みで解決。これが行動経済学のやり口だね
世の中を「自分vs他人」の問いではなく、設計のバグを直すゲームとして見ることが出来るようになる。
「ズルする人を取り締まるには?」→罰則だけでなく、仕組み自体をズルできない設計にすることが重要
経済学的には「人はズルする」前提で考え、倫理には期待しすぎない。
正しさを押し付けなくても、自分に得にならなければズルは減る。
得になる仕組みを変えれば行動も変わる。
「正しいことを促す仕組み」をどう作るかがカギ → 感情じゃなく「構造」で考える視点。
自分を責めすぎないこと。
他人を責めすぎないこと。
社会を変えるなら、「仕組み」から
人間は完璧じゃないし、モラルだけでは動かない。だから「どうすればうまく回るか」って仕組みを考えるのが経済学
「正義より構造が人を動かす」
誰かを変えるよりも、仕組みをちょっと変えるほうが 結果が早いかも。
世界をうまく回すのは、人の心だけじゃない。
でも、仕組みだけでも足りない。
感情と理性、思いやりと設計。
どっちも必要。



優しい人が損するような仕組みは、ちょっと設計ミスだな。
まとめ:この本から得られること
- 「やる気」は設計ミスで消える
- 「ズル」は構造のバグで起こる
- 善意は時に、報酬で壊される
→「責めるより、仕組みを見直そう」
そう思えたら、ちょっとだけ心が軽くなります。
「頑張ってるのに評価されない」「どうせ私は向いてない」
そんな風に思い詰める前に、ちょっと“仕組み”の目線で世界を見直してみてほしい。
さて、最初にピンカーンが言っていた「魔法の言葉」の答えです。
「今日は3件まわって見積もりをもらう予定なんですよ。」
大きな買い物をする際はぜひご活用ください。
ご注文はこちらからどうぞ
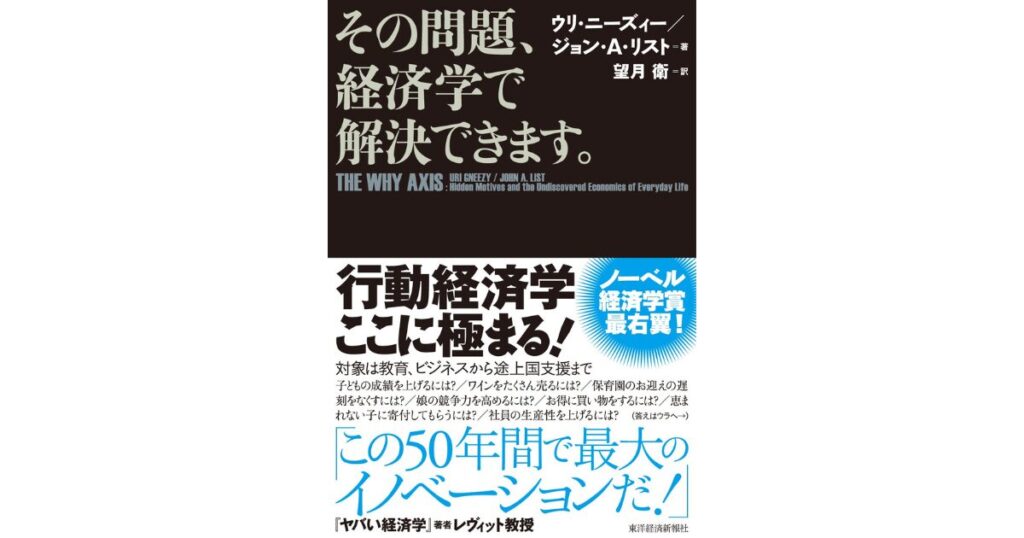
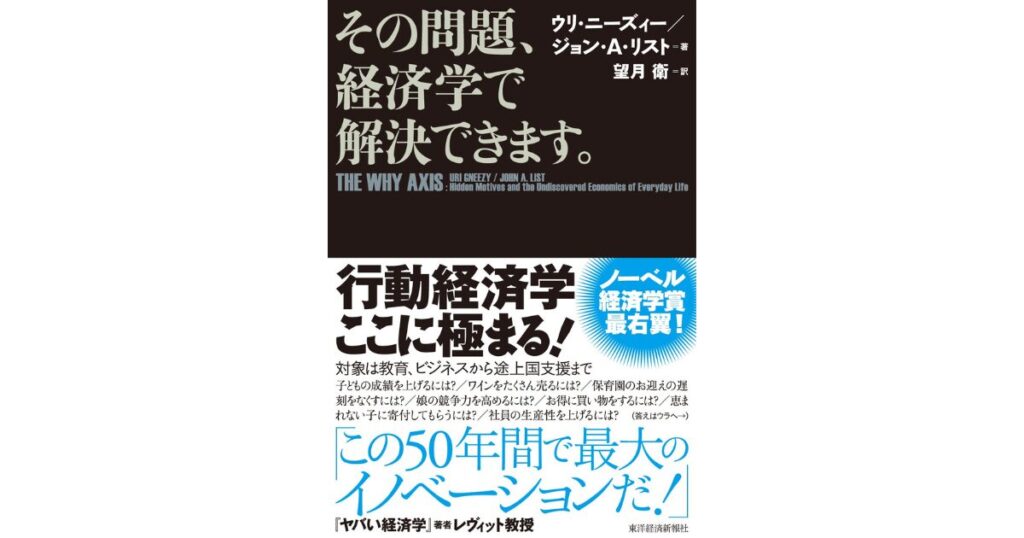
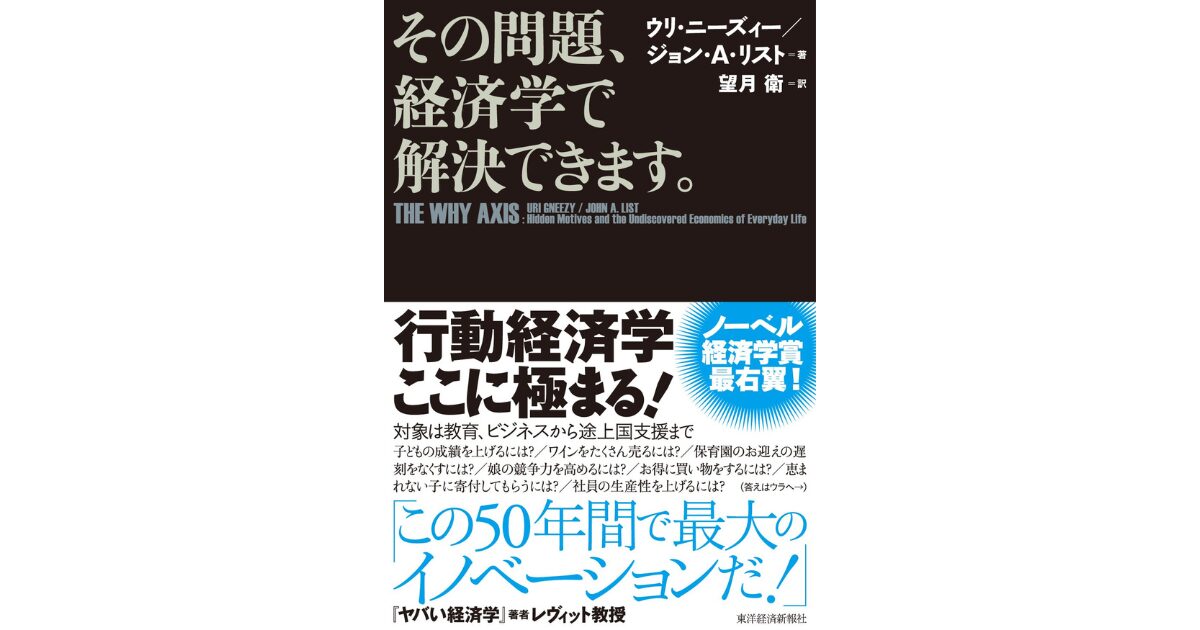
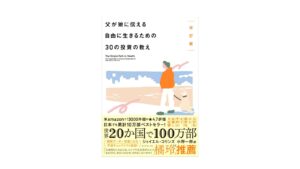

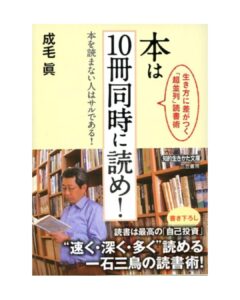


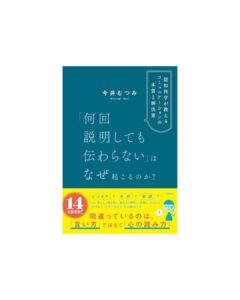
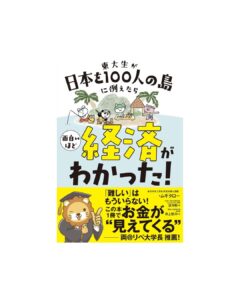
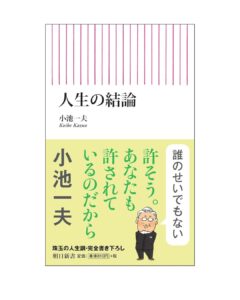
コメント